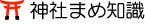 |
| 神棚のおまつり(家庭祭祀) |
| 国旗・日の丸 |
 |
日章旗とも云い、日本の国名にもちなんだ日輪を形どる。日輪を尊ぶ気風は、農耕民族の故であろうか。またわが国の神話伝説に由来し、自然の(太陽の)恵みに感謝順応している。
推古天皇また、文武天皇の大宝元年の儀式で日章の幟を建てられた記録がある。豊臣秀吉、山田長政、徳川幕府も日の丸を揚げたという。明治政府は明治3年1月27日、太政官布令により規定を定めた変遷があり、平成11年国旗国歌法が成立し、長年の慣習が法律により明文化された。 |
|
| 国歌・君が代 |
 |
歌詞は古歌で、多くの人々に愛唱されてきた君が代が国歌に選ばれ、明治13年の天長節に公表された。作曲は林広守。明治26年8月12日、文部省は告示第三号を以て祝祭日の式典用唱歌として公布した。歌詞の出典は古今和歌集の歌が基である。 |
|
| 神棚の位置 |
 |
南、または東向で、家の一番良い所の目の高さより少し上に設ける。かまどの神様は、かまど、ガスコンロのある所に設ける。
正月には神棚の正面上に清めた場所を意味する注連縄を飾り榊立ても一対設けるのがふさわしい。 |
|
| 家の神様 |
 |
社一座の場合は手前から神宮大麻、氏神様、崇敬神社のお札を重ねてまつる。
社二座の場合は向かって右に神宮大麻、左の手前から氏神様、崇敬神社の神札をまつる。
社三座の場合は中央に神宮大麻、向かって右に氏神様左に崇敬神社の神札をまつる。 |
|
| 朝のお供 |
 |
お供えは洗米(ごはん)、塩、水は必ずお供えし、この他、海魚、乾物、野菜、果物などを供える。葱、玉葱、ニンニク、等のにおいの強いものは供えない。毎月一日、十五日、行事ある日はお神酒を供える。
|
|
| お供の順序 |
 |
お供えの一位は中央、二位はその右、三位はその左等次のような順序にする。
洗米、酒、餅、魚、乾物、野菜、果物、塩、水。
三方のつぎ口を手前にし、用具は八寸の三方などが標準的で皿(カワラケ)酒器(ヘイシ)などを時々新調すれば清浄になる。
平素は三方に洗米、塩、水をお供えし、榊は両側、灯明も一対とする。
お供えがすめばお祈りをする。
先ず二度礼、次にお祈り、
「○○家のご神前に申し上げます。今日一日家族一同、神様のおめぐみに感謝し清正しく、無事に暮らすことが出来ますようにお守り下さい。」
次に二度礼、二拍手、一礼。
お祈りは家族一同、神棚の前で行う。特に子供とはいっしょにお参りする。座布団は使用しない。 |
|
| 夕のお参り |
 |
拝礼の仕方は前項と同様。
「○○家のご神前に申し上げます。今日一日のみめぐみにより清く正しく無事にすごすことが出来ました。今日一日の感謝を申し上げます。」 |
|
| 紙垂の切り方 |
 |
半紙を半分に切り、それをまた半分に切る。それを二つ折にして、次のように切って一対作る。
|
|
| 依 代 |
 |
祭に当たって神霊が降臨するための標示物を云う。樹木、石等の自然物の場合と、幟、柱、御幣(ごへい)、等の舗設の場合がある。神道祭祀の形態では、樹木が伝統的な依代である。(木霊、御神木等) |
|
| の し |
 |
熨斗鮑(のしあわび)のことで、鮑の肉を細長く切り、のばして干したもの。古来長寿の薬として鎌倉時代よりお祝いに添える習慣が生まれた。
伊勢神宮の祭典には、志摩の熨斗鮑がお供えされる。
祝儀袋の右上に付けてある熨斗(印刷)は、これを略式にしたものである。 |
|
| 家庭のまつり |
 |
家が建ち、新しい生活が始まります。これからも日々の暮らしを末永く見守っていただくために、お神札をおまつりしましょう。神棚に「伊勢の神宮」と「地域の氏神さま」のお神札をおまつりすることで、日常生活のなかにも、神さまとのつながりを実感することができます。いつも見守ってくださっていることへの感謝の心を持ち、神棚に向かい、心を落ち着かせてから一日をスタートする。そんな習慣を身につけてみてはいかがでしょう。
 |
 |
| ※お紙札は図の位置、順番で、宮形の中におさめます |
|
|
| 神棚とマンション |
 |

「神棚を設けるスペースがない」「家の雰囲気に合わない」などの理由でお神札をおまつりするのをためらっていませんか?そんな場合は、箪笥や本棚などの上に白い紙をしき、そこにお神札をおまつりしても大丈夫です。
大切なのは神さまを敬い真心をこめておまつりすることです。 |
|