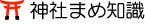 |
暦の見方
こよみは日読で、日をよんで数える意味。太陽の出没によって、年月を組合せ、暦をたてたものを太陽暦と云い、月の満欠で年月の組合せを作った暦を太陰暦と云う。
暦には日の他に、七曜、干支、旧の日、六曜、二十八宿、十二直などがあり、暦注といって二十四節、七十二侯、祝日、年中行事、祭礼、その他生活に即した事項が書き入れてあるがこれらを簡単に説明する。 |
| 新暦の日 |
 |
現在用いられている新暦の日は、明治五年十一月九日、太政官布告によって定められた。一年を三六五日、または三六六日として、これをはぼ三対一の割合で繰返し、その平均の長さを季節の一周の平均の長さ、三六五日、二、四二二にほとんど等しくするもの(三千年後に日付と季節とが平均一日喰違う)で毎年の日付は季節を示す。 |
|
| 旧暦の日 |
 |
一ケ月は二十九日か三十日とし、これを一対一の割合で繰返し、平均の長さが月の満ち欠けの一周の平均の長さ、二十九日、五三〇五八八にはとんど等しく、毎年同じ日付ははとんど同じ月相を示す。すなわち月の十五日頃が満月となる。
月によって日をきめるのに二通りあり、純太陰暦は一年を常に十二ケ月、三五四日、または三五五日とする。この暦は太陽暦にくらべると、一年間に十一日短く、三十三年で一年進むことになる。それで、三十年暦に十一回の閏年(三五五日)をおいて調節するがやはり季節とはなれる。回教暦はこの方法をとっている。
太陰太陽暦は一年を十二か月または十三か月とし、これをほぼ十九対七の割合で繰返して、平均の長さを季節の一周の長さ三六五日、二四二二にほば等しくして日付が大略の季節を示すようにしたもので、日本の旧暦の日の取り方はこれによっている。 |
|
| 七 曜 (しちよう) |
 |
七という日のとり方に二系統があり、
1、日の周期が約二十八日でそれをさらに二つに分けて七日ずつとした。
2、肉眼で見える惑星(火木土金水星)に太陽と月を加えて七とした。
このように日曜、月曜という七曜は西洋からはいって来たものではないが、七曜にあたる考え方は、ユダヤにおいて七日ごとに安息日を数えており、キリスト教をとおしてヨーロッパに広まっている。日曜を神聖な日として労働休日とするのは西洋から世界に広まっている。 |
|
| 干 支(かんし) |
 |
干支とは、十干、十二支のことで、もとは 十干は一旬十日を記すため、十二支は月にあてるためにつくられたものである。(陽即ち兄・陰即ち弟)。
十干十二支
| 甲(キノエ) |
乙(キノト) |
丙(ヒノエ) |
丁(ヒノト) |
| 戊(ツチノエ) |
己(ツチノト) |
庚(カノエ) |
辛(カノト) |
| 壬(ミズノエ) |
癸(ミズノト) |
|
|
十二支
| 子(ね) |
丑(うし) |
寅(とら) |
卯(う) |
| 辰(たつ) |
巳(み) |
午(うま) |
未(ひつじ) |
| 申(さる) |
酉(とり) |
戌(いぬ) |
亥(い) |
十二支を月にあてる場合は正月を寅としてはじめる。閏年の十三(閏年の十三ケ月日の意)月は寅で翌年の一月もやはり寅からはじめる。 |
| 時間 |
十二支と方向 |
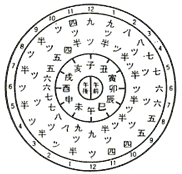 |
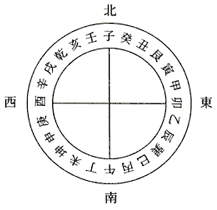 |
|
|
| 六曜または六輝 |
 |
中国から日本に伝わった時は大安、留連、連喜、赤口、将吉、空亡の六つで時刻の吉凶占いであったから、時刻占いの要素を残しているが、友引に葬式をしないなどの民間の考え方は暦にはない。
 先勝 諸事急ぐことによく午後より悪し 先勝 諸事急ぐことによく午後より悪し
 友引 朝夕よし正午より悪るし 友引 朝夕よし正午より悪るし
 先負 諸事静かなることよし、午後大吉 先負 諸事静かなることよし、午後大吉
 仏滅 万事凶、口舌を慎むべし、患えば長引く 仏滅 万事凶、口舌を慎むべし、患えば長引く
 大安 移転、開店、婚礼等万事利あらざることなし、大吉 大安 移転、開店、婚礼等万事利あらざることなし、大吉
 赤口 諸事ゆだんすべからず、用いるは凶、正午少しよし 赤口 諸事ゆだんすべからず、用いるは凶、正午少しよし
に配するには一月から各一日に先勝から以下順に配し冬日も、また一日の六曜から順にはじめる。 |
|
| 十二直(じゅうにちょく) |
 |
十二直を方位に配して(十二支と方位参照)北斗七星を斗(柄杓)と見、正月には斗柄は寅の方向をさすから、正月(寅の月)の節目のあと、はじめての寅の日を建とし、二月の節日のあとはじめて卯の日を建とする。以下一つづつ、ずらして、建にあたる日を三月は辰、四月は巳、五月は午、六月は未、七月は申、八月は酉、九月は戌、十月は亥、十一月は子、十二月は丑、十三月は寅として配する。
北斗の斗柄が寅の方向を指すのを見て歳のはじめと定め、その寅の月を正月としたのが暦法の根本である。
北斗崇拝は宿曜道、陰陽道、道教系のものであるが、真言宗では北斗を祭る北斗法を最大の秘法とし、中世以降には星祭りがあらわれた。このため北斗を本地とする妙見菩薩信仰が出来て全国各地に妙見堂がある。
| 建(たつ) |
大吉、万よし、土をうごかし、船のりは悪し |
| 除(のぞく) |
わるきことよける日、物を捨てる大いによし |
| 満(みつ) |
神まつり、移転、婚礼、開店、たねまき、土を動かす等よし |
| 平(たいら) |
よしあしともに平か、相談ごとには大いによし |
| 定(さだん) |
婚礼、井戸堀など万事定めごとには大いによし |
| 執(とる) |
五穀の取入れ、買入れすべて手に入れることよし |
| 破(やぶる) |
約束、相談その他のとり決めなどによろしからず |
| 危(あやぶ) |
何事にもあやうき日故、旅立、船のりなどにわるし |
| 成(なる) |
金談、その他、開店、披露、柱立などに用いて大いによろし |
| 収(おさん) |
この日はおさむると云う日故、収穫、その他諸事に用いてさわりなし |
| 開(ひらく) |
この日は入学、開業、諸事前途の望み遂げるによし、進んで大吉 |
| 閉(とづ) |
開店、その他万事に悪日、墓石立つるに吉 |
|
|
| 二十八宿(にじゅうはっしゅく) |
 |
月が全天を一周するのに二十七日半弱かかる。それを星座として示したのが二十八宿で、吉凶の信仰がある。
( )内カタカナは読み、ひらがなは日本の星名。
| 角(カク・すぼし) |
棟上、婚礼万事吉、葬式凶 |
| 亢(コウ・あみぼし) |
婚礼、種蒔、衣類裁吉、造作等凶 |
| 氐 (テイ・とも) |
婚姻、入宅、酒造、店開、かまど作、種蒔など吉、衣類裁凶 |
| 房(ボウ・そい) |
棟上、造作吉、嫁取、田畑を求むるは凶 |
| 心(シン・なかご) |
神祭、仏供養吉、造作、婚礼移転凶 |
| 尾(ビ・あしたれ) |
婚礼、造作、店開吉、衣類裁凶 |
| 箕(キ・み) |
池、溝、庭作り、宝収によし、嫁取り、衣類裁吉、以上東(蒼竜・青竜) |
| 斗(ト・ひきつ) |
裁ち縫、蔵立、池ほり吉 |
| 牛(ギュウ・いなみ) |
万事よし、午のときは大吉祥 |
| 女(ジョ・うるき) |
芸を学ぶによし、着初めよし、葬式凶 |
| 虚(キョ・とみて) |
衣類裁ち縫、着初、学問はじめによし |
| 危(キ・うみやめ) |
凶日、家造、壁ぬり、かまどぬり、酒造よし |
| 室(シツ・はつい) |
嫁とり、井戸堀、仏事吉 |
| 壁(ヘキ・なまめ) |
婚礼、旅行、造作吉、南に行くは凶、命名等凶、以上北(玄武) |
| 奎(ケイ・とかき) |
衣頬裁吉、開店、門開、蔵開大凶 |
| 婁(ロウ・たたら) |
開店、衣類裁、着初吉、婚礼大吉 |
| 胃(イ・えきえ) |
家建、衣類裁、掛合、金談など私事に凶 |
| 昴(ボウ・すばる) |
神仏祈願、供養吉、造作凶 |
| 畢(ヒツ・あめふり) |
神祭、造作葬式、動土吉 |
| 觜(シ・とろき) |
入学、杣入りよし、衣類裁凶 |
| 参(シン・からすき) |
養子とり、門立、造作によし、衣服裁凶、以上西(白虎) |
| 井(セイ・ちちり) |
神事、造作、井戸堀、種蒔吉、衣類裁凶、以下南(朱雀) |
| 鬼(キ・たまほめ) |
万事吉、神仏詣、家造、井戸掘、かまどぬり吉、婚礼凶 |
| 柳(リュウ・ぬりこ) |
杣入り吉、造作、葬式、衣服裁にわろし |
| 星(セイ・ほとほり) |
馬乗始、厩造等吉、婚礼、葬式、衣服裁、種播凶 |
| 張(チョウ・ちりこ) |
神仏に祈り、また奉公するなどに最もよき日 |
| 翼(ヨク・たすき) |
衣服裁、農事は種蒔吉、高き所の家造り凶 |
| 軫(シン・みつかけ) |
棟上、厩造、橋掛、井戸掘、嫁取、社参、入学、衣服裁によし。 |
太陰はおよそ一日に一宿ずつ運行する。 |
|
| 九 星(きゅうせい) |
 |
一から九までを、たて、よこ、ななめに並べて、十五になるように配列することが出来るが、これを魔方陣(マジックスクエァ)とよび中国では神秘な扱いをして釆た。隋から唐の時代にかけて作られたのが九星で運命を判断出来るとした。
九星は五を中心として、九つの数字に五つの色、五つの星を配当する。中央を中宮と云いその人の生まれた年に中宮にあった星をその人の本命と云う。五黄殺、暗劔殺の方位を定め凶の方向とする。 |
| 九星の定位 |
魔方陣 |
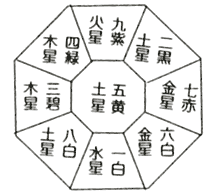 |
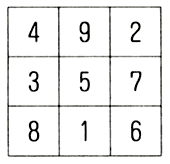 |
| 年に寄って配置が変わる |
|
|
|
| 八将神(はっしょうしん) |
 |
中国で出来た暦法の吉凶をつかさどる八神、巡り神で年によってそれぞれの神のいる方向が違う。向位は十二支にあててきめる。
| 太歳神(たいさいじん) |
木星の精、人君の象で諸神を率領して時序を幹運し歳坊を総成する。その年の十二支の方位にある。この方に向いて木を伐らず。 |
| 大将軍(だいしょうぐん) |
太白(金星)の精で武臣統御この方三年ふさがり。 |
| 太陰神(だいおんじん) |
鎮星(土星)の精、太歳神の后、この方に向いて産をせず。 |
| 歳刑神(さいきょうしん) |
水星の精で刑殺を司る、種蒔は不作凶。 |
| 歳徳神(さいとくしん) |
一年中の万徳を司る太歳神に同じ。あきの方、正月のトシの神と同一視する信仰が生じた、この方位大吉、恵方。 |
| 歳破神(さいはしん) |
土星の精いつも太歳神と向い合う。転宅旅行不可。 |
| 歳殺神(さいせっしん) |
金星の精で陰気はなはだしい。毒害の方、婚礼、養子不可。 |
| 黄幡神(おうばんしん) |
羅暇(らご)星の精で、新規普請、損多し。 |
| 豹尾神(ひょうびしん) |
計都星で豹のように動くという。畜類求むる不可。 |
|
|
| 金 神(こんじん) |
 |
中国で出来た暦法。陰陽道でまつる方位の神。金神は太白(たいはく)、すなわち金星の精と云う。金神と同じようなものに大金神、姫金神があって、八将神の外で所在が変るという信仰がある。金神にたたられるとおそろしいと云われる。
| 金 神 |
年によってその方位を異にし、季節、日によっても変ると云われている。 |
| 大金神 |
将軍方位で、今年の支より逆に数えて四番日の支の方向にある。 |
| 姫金神 |
大金神対応の方向にある。 |
|
|
| 暦注事項 |
 |
十四節、中国系季節区分で十二の節(気候の変り目で時節を意味する)と十二の中(時侯季節を意味する)から出来ており二十四節を分けて七十二侯を立てる。
七十二俣、一侯は五日とする。(五日ごとに季節が変ってゆくとした)。
| 陰暦月 |
節 |
七十二候 |
中 |
七十二候 |
| 一月 |
立春 |
1 東風氷を解く
2 蟄虫はじめて動く
3 魚渉りて水を負う |
雨水 |
4 獺魚を祭る
5 鴻雁北へ行く
6 草木萌し動く |
| 二月 |
啓蟄 |
7 桃はじめて華く
8 倉庚鳴く
9 鷹化して鳩となる |
春分 |
10 つばめ至る
11 雷声を発す
12 始めて雷す |
| 三月 |
清明 |
13 桐はじめて華く
14 田鼠化して鶉となる
15 紅はじめて見ゆ |
穀雨 |
16 浮草はじめて生ず
17 鳩その羽を払う
18 戴勝桑に降る |
| 四月 |
立夏 |
19 螻蛄鳴く
20 蚯蚓生ず
21 王瓜生ず |
小満 |
22 苦菜秀ず
23 靡草死す
24 麦秋至る |
| 五月 |
芒種 |
25 蟷螂生きる
26 鳩はじめて鳴く
27 反舌声なし |
夏至 |
28 鹿の角解つ
29 蝉はじめて鳴く
30 半夏生ず |
| 六月 |
小暑 |
31 はじめて温風至る
32 蟋蟀壁に居る
33 鷹はじめて摯る |
大暑 |
34 腐草螢となる
35 土潤ってあつし
36 大雨時に行る |
| 七月 |
立秋 |
37 涼風至る
38 白露降る
39 寒蝉鳴く |
処暑 |
40 鷹すなわち鳥を祭る
41 天地はじめて粛る
42 禾すなわち登る |
| 八月 |
白露 |
43 鴻雁来る
44 玄鳥帰る
45 群鳥羞を養う |
秋分 |
46 雷はじめて声を収む
47 蟄虫戸を坏ぐ
48 水はじめて涸る |
| 九月 |
寒露 |
49 鴻雁来賓す
50 雀水に入って蛤となる
51 繭に黄色あり |
霜降 |
52 豺すなわち獣を祭る
53 草木黄落す
54 蟄虫ことごとく俯す |
| 十月 |
立冬 |
55 水はじめて氷る
56 地はじめて凍る
57 雉水に入りて蜃となる |
小雪 |
58 虹蔵て見えず
59 天謄り地降る
60 閉寒冬をなす |
| 十一月 |
大雪 |
61 やまどり鳴かず
62 虎はじめて交わる
63 茘梃出づ |
冬至 |
64 蚯蚓結ぶ
65 鹿角解つ
66 水泉動く |
| 十二月 |
小寒 |
67 雁北に郷う
68 鵲はじめて巣う
69 雉なく |
大寒 |
70 鶏乳す
71 征鳥はじめて疾ぶ
72 水沢腹堅し |
|
|
| 二至二分(にしにぶん) |
 |
春分、秋分、夏至、冬至を云う。 |
|
| 節 分 |
 |
節分は立春の前日、立春は太陽が黄経三一五度に来る日を指し、太陽暦による節を分ける日。
節は二十四節のことで、節分はその代表。春夏秋冬のはじめに四回の節分があったが、他は忘れられて春の節分だけが残っている。節分を年越しと云うのは、次の日が立春で、正月の前日であったからである。年越しの夜に豆を播くのは大祓であると考えられる。 |
|
| 社 日(しゃにち) |
 |
中国では社日は春と秋にあって、春の社日には五穀の種を播いて豊熟を祈り、秋の社日には、稔った作物の初穂を供えて感謝した。社は中国では村のヤシロを意味した。春分秋分に一番近い戌の日が社日である。 |
|
| 入 梅 |
 |
夏至からかぞえて十度(黄経八十度)前を入梅とする。
太陽暦で六月十一日頃に当る。 |
|
| 土 用 |
 |
用は曜で盛んな意で、春夏秋冬それぞれもっとも盛んな時が土用である。暦の土用は土用の入を示したもので土用は十八日間ある。 |
|
| 八十八夜 |
 |
立春からかぞえて八十八日目の日を云う。晩霜の終りの目安であり、播種の適期とされる。 |
|
| 二百十日 |
 |
立春からかぞえて二百十日目、中稲の開花期で台風の上陸する頃である。 |
|
| 朔 望(さくぼう) |
 |
旧暦で朔はついたち(月立の意)、望はもち月(満月・十五日)の日、つごもりは月の隠れる時で月末である。 |
|
| 天一天上(てんいちてんじょう) |
 |
天一神(艮神)が天上に帰る日を天一天上と云う。天一神はみずのとみ(癸巳)の日が天上に帰る日で、その日からつちのえさる(戊申)の日までは天上にあり(十六日)、つちのえとり(戊酉)の日からみずのえたつ(壬辰)の日までは方を変えて地上にいる。天上にある日を天一天上といって障りなし、天上より降って八方をめぐっている間はその方を忌む。荒神と信じられ、方達はこの神の方位をさけることである。 |
|
| 八 専(はっせん) |
 |
壬子の日から癸亥までの十二日問を云い、そのうちの丙辰、戊午、壬戌、癸丑、の四日は間日、残りの八日を専日(せんにち)と云い、一年に六回ある。専日は干支が同気で気が偏専しているから平和でなく、鍼灸を忌むが、柱立、棟上げなどに良いと云う。 |
|
| 十方暮(じゅっぽうくれ) |
 |
甲申の日から、癸巳の日まで十日問を云い、五行が相剋して十方不和であるから、出向を忌む。万事に凶とされる。 |
|
| 三 伏(さんぷく) |
 |
播種、療病、旅行を忌む日。夏至の第三の庚(かのえ)を初伏、第四の庚を中伏、立秋後の第一の庚を末伏とする。時候の挨拶で極暑の候を云う。 |
|
| 天赦日(てんしゃにち) |
 |
暦注の一。上吉の日。万事に障りなし。 |
|
| 凶会日(くえにち) |
 |
凶日、陰陽相剋して万事に凶である。 |
|
| 三隣亡(さんりんぼう) |
 |
この日造作をすれば、隣家三軒を亡ぼす悪日。旧正月、四、七、十月は亥の日、二、五、八、十一月は寅の日。三、六、九、十二月は午の日。 |
|
| 不成就日(ふじょうじゅにち) |
 |
陰陽道で一切の何をやっても成就しないとして忌む日。不成日。 |
|
| 一粒万倍日 |
 |
一粒が万倍になって、稲穂のようにみのる日で、種播の吉日、借金は凶。 |
|
| 土 公(どこう) |
 |
土を守る神で、この神の方位もおかしてはならない。春は竈に、夏は門に、秋は井に、冬は庭にあって、その場所を動かすことを忌む。 |
|
| 大・小の月 |
 |
大の月は、太陽暦で三十一日、太陰暦では三十日の日数がある月。太陽暦では一月、三月、五月、七月、八月、十月、十二月である。
小の月は、太陽暦で一カ月の日数が三十日以下の月。すなわち二月、四月、六月、九月、十一月の五カ月をさす。太陰暦では一カ月の日数が二十九日以下の月を云う。 |
|